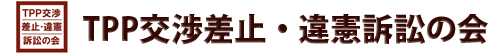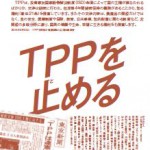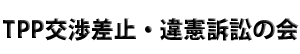6月28日に行われた「種子法廃止等違憲訴訟」の第4回口頭弁論期日で、3人目となる原告意見陳述を行った舘野廣幸さん。館野さんは栃木県で有機稲作農家として「館野かえる農場」を営んでいる。「種と農家を守ることは、国民の食糧を確保する国としての責任。種子法は廃止ではなく、むしろ拡充するべき」という訴えに込めた思いを伺った。
農家の声を聞かずに「廃止」。国は農業を見捨てたのか
私は栃木県南部の野木町で、農薬や化学肥料を使わず有機農業で稲作を30年間続けている専業農家です。「館野かえる農場」という名前は、稲を害虫から守り、有機農業を支えているのは「かえる」たちであるということから命名しました。
私の農場では、コシヒカリなど数種の米を栽培していますが、主要農作物種子法 (以下、種子法)に基づいて栃木県から日本で初めて有機栽培種子の採種ほ場として指定された「NPO法人民間稲作研究所」より購入した種子で栽培して、翌年から3世代(3年間)は自家採種した種を使っています。ずっと自家採種した種だけで栽培すると性質が変わってしまい、特定の品種として認められない可能性があるからです。
有機農業は、種子から無農薬、有機栽培であることが原則です。ところが、日本では有機の種子を供給する体制が整っていません。「NPO法人民間稲作研究所」が供給できる有機種子の量も限られてます。国は有機農業推進法(※1)やみどりの食料システム戦略(※2)などを作って有機農業を推進しましょうと掛け声をかけていますが、材料がなければ作ることはできません。種子法を廃止するよりも、本来は一般種子の生産に有機種子の生産体制も加えて強化すべきだと思います。
昔は、ほとんどの農家が米も野菜も自家採種をしていました。戦争や災害など社会状況によって種が手に入らなくなることもあり得たからです。もしそうなれば次年度の生産ができません。それが戦後に種子法が制定され、 米や麦、大豆などについては国や県が安定した種子供給を約束したことで変わっていきました。農家は作物の生産に専念できるようになったのです。
ところが、今回の種子法廃止で、急に「もう国は責任をとりません。主要作物の種子も民間企業から買ってください」ということになってしまいました。なぜ一番大きな影響を受けるはずの農家の意見さえ聞かずに決めてしまったのか。国は農業を見捨ててしまったのではないかと感じます
米の原種価格が3倍以上に。国民の食糧を守るのは国の責任
種子法廃止によって、農家には「種子を安定して入手できないのではないか」という非常に大きな不安があります。栃木県では種子条例ができましたが、その中身はひどく、育種ほ場の選定や審査、品質管理などを農家の自己責任にして、県は種子生産に責任を持たないようなものになっています。
さらに、すでに種子の価格にも異変が起こっています。これまで栃木県から配布される米の原種の価格は1kgあたり465円でしたが、今年3月に「NPO法人民間稲作研究所」に届いた原種の請求価格は1,548円と3倍以上になっていたのです。
当然、その原種から作る種の価格も高くなります。だからといって農家が生産する米の価格が上がる見込みはなく、むしろ米価は下がっています。これでは、ますます農家は辞めていくでしょう。そうなれば結局、日本の農業全体が衰退していきます。
しかも、種子法が廃止されて種子の安定供給が危ぶまれる一方で、種苗法改正によって登録品種の自家採種に許可が必要になりました。農家としての権利や自由がどんどん奪われていく思いです。
少なくとも国民の主食になる米、大豆、麦などの種子を守ることは、国の責任であると私は思っています。「種子を守る」「農家を守る」ということは、食糧を確保して国民の命を守ることにつながります。種子法廃止は、国民を捨てて民間企業を守る動きです。しかし、民間企業というのは利益を優先するもの。国民の食糧供給の源泉である種子を国が政策として守らないのなら、誰が国民の生命を守るのでしょうか。
国は種子法を「廃止」するのではなく、むしろ「拡充」するべきです。いま全国では貴重な在来種子が失われつつあります。こうした在来種子も国の財産として守るべきですし、有機栽培を推進するために有機種子のほ場を確保する必要もあります。手間がかかり利益の出ない有機の種子を民間企業が作るとは思えません。
種子法の廃止というのは、国が農業を見捨て、国民の生存と生活の保障を放棄したのと同じだと私は考えています。
※1: 2006年12月施行。化学的に合成された肥料と農薬を使わず、遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本とし、環境負荷をできる限り減らした農業を「有機農業」と定義し、農業者が有機農業に取り組めるよう国と自治体に支援を義務づけている。
※2: 2021年5月に農林水産省が策定。環境に配慮した持続可能な農林水産業を目指し、2050年までに「有機農業の面積を耕地全体の25%に拡大」するなどの目標を掲げている。
プロフィール
舘野廣幸 (たての・ひろゆき)
栃木県で「館野かえる農場」を営む。米、小麦、大豆などを、化学合成肥料や農薬などを使用しない有機農法にて耕作。米は自家採種した種もみ(稲種)と、種子法に基づいて有機栽培用種子の採種ほ場として指定を 受 け た「 NPO法人民間稲作研究所」が生産した種もみを使用。
Text: Mie Nakamura