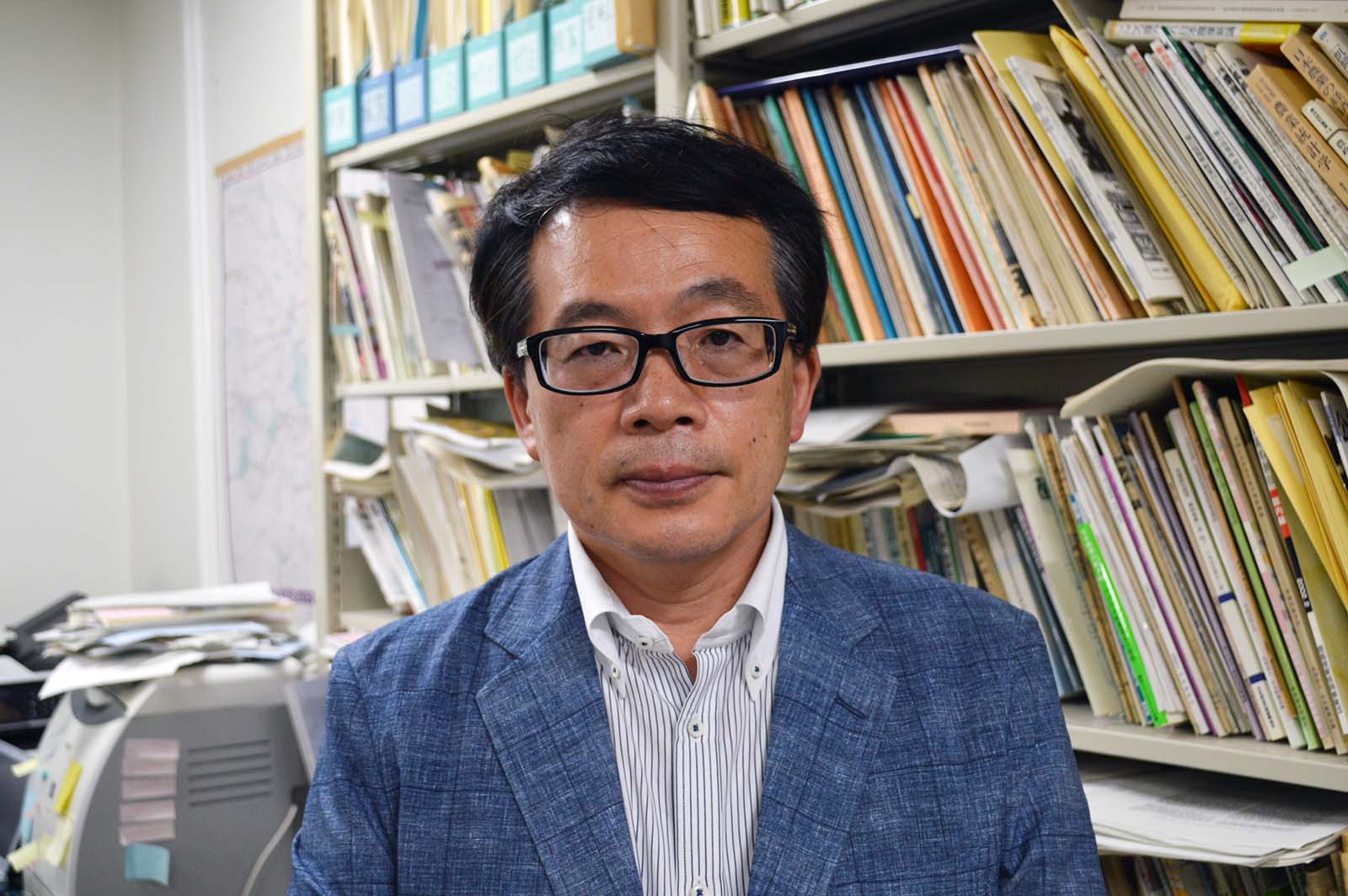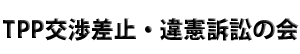6月3日に行われた第7回口頭弁論期日の証人尋問では、農業経済学者である東京大学大学院教授の鈴木宣弘さんが証人として立ち、日本の食料自給率の危機的状況、種子法廃止に至る政策決定プロセスの問題点について指摘した。今回の期日で提出された意見書の内容とあわせて、改めて鈴木さんに話を伺った。
日本の「食料安全保障」は破綻 追い打ちをかける種子法廃止
世界的な食料危機の要因として「クワトロショック」(コロナ禍、中国による大量の食料輸入、異常気象、ウクライナ紛争)と呼ばれるものがあります。
小麦を例にみると、ロシアとウクライナが輸出量の3割を占めていますが、ロシアは「もう売ってやらないぞ」と食料を脅しの道具にしている状況で、ウクライナは思うように輸出できていません。さらに、食料危機を受けて、自国民を守るために輸出を制限している国が20カ国もあります。日本は小麦をアメリカやカナダなどから買っていますが、世界の需要が集中して争奪戦が起き、買い負けるようになってきています。
これまで日本政府は「お金を出せばなんでも買える」ことを前提に、国内農業をないがしろにして輸入の依存度を高めてきました。しかし、その前提は完全に崩れてしまった。食料安全保障のために、しっかり自給率を高めることを考えなくてはいけません。
こうした状況にもかかわらず、日本は種子法廃止で、公共のものとして守ってきた主要作物の種子まで民間企業に委ねる方向を決めてしまいました。すでに民間企業の種子が主流の野菜をみると、日本の種子企業が販売していても、その採種は9割が海外の圃場に委託されています。そのため、コロナ禍で物流が止まったときには、「種が入ってこないんじゃないか」と大騒ぎになりました。同じような状況が進めば、2035年時点には米の実質自給率が最悪11%にまで下がることも想定されます(※1)。種子法廃止が日本の農業と国民の命を守る意味でいかに大きなリスクかがわかります。
これは、食料自給率向上を目標に掲げる食料・農業・農村基本法の基本理念にも反するもの。このような重大な法の廃止は、本来は食料・農業・農村政策審議会(農政審議会)で民主的なプロセスのもとに審議されるべきでした。もし審議されていたら通らなかったでしょう。しかし、国会での審議時間もほとんどとらず、農政審議会にもかけず、ほとんどの人に知らせないまま決めてしまった。その背景には、「種を制する者は世界を制する」というグローバル種子・農薬企業の要請があります。
民主的過程を無視した政策決定 国民の命のリスクを高めるもの
種子法廃止が農水省の意図を超えた異常な決定だったことを示す事実として、種子法廃止後の悪影響を抑えようと、都道府県が従来通りの種子生産事業が続けられるよう事務次官通知を出す準備をしていたにもかかわらず、「上」からの一言で内容が変えられ、「県が継続して事業を続けるのは企業に引き継ぐまでの期間である」という文章が入れられたことがあります。
この状況はTPP協定とも関係しています。日米2国間のサイドレターによる合意は生きていて、アメリカの企業が日本にやってもらいたいことを日本は規制改革推進会議を通じて実行する約束になっているのです。規制改革推進会議から「これをやりなさい」と流れてきたことには、政治も行政も関連組織も全く反対できず、もはや審議会も機能していません。同じようなことが種子法だけでなく、森林関係の法律や漁業法の改定でも起きています。
「今だけ、金だけ、自分だけ」の日米の巨大企業と結びついた人たちが、自分たちの儲けだけを考えて法律制度の改定を強行しており、世界的な食料危機や国内農家の苦しい状況があるにもかかわらず、対策をとろうとしない。公共の種子を失うことは安全保障上も大きなリスクです。有事のときに物理的に種子が入ってこなくなれば飢餓が起きかねず、「種を止めるぞ」と脅されたら従わざるを得ない。食料の自給ができなければ、もはや独立国ではないのと同じです。
民主的な政策決定を逸脱して決定された種子法廃止は、食料・農業・農村基本法に反するだけでなく、食料の源である種子を奪われた国民の命のリスクを著しく高めるものだと言わざるを得ません。
※1:令和3年度の米のカロリーベース自給率は98%。種の自給率が10%になると、2035年の推定自給率は11%となる(鈴木宣弘研究室試算)
プロフィール
農業経済学者
鈴木宣弘(すずき・のぶひろ)
東京大学大学院農学生命科学研究科教授。専門は農業経済学。農林水産省、九州大学大学院教授を経て現職。FTA産官学共同研究委員、食料・農業・農村政策審議会委員、経産省産業構造審議会委員、コーネル大学客員教授などを歴任。
Text: Mie Nakamura