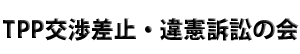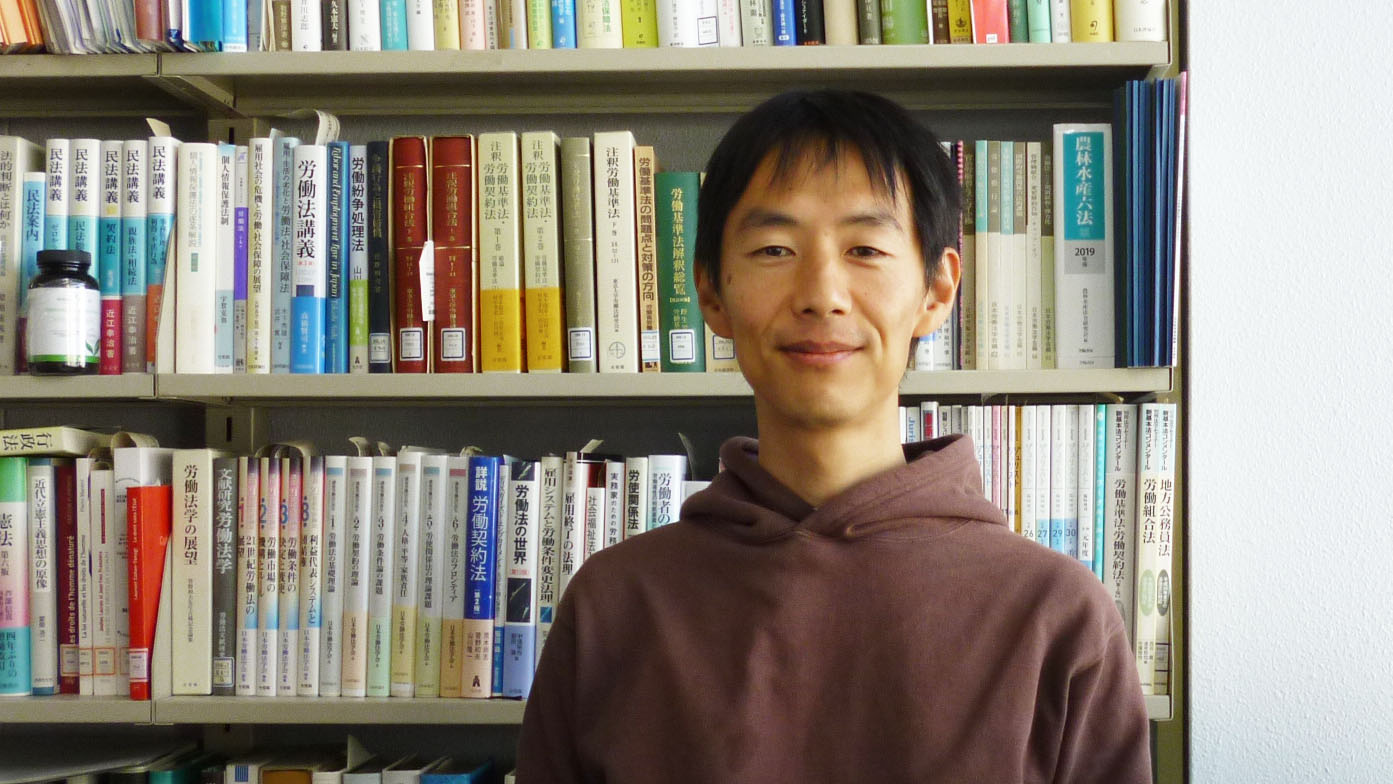
「種子法廃止等に関する違憲確認訴訟」の原判決は、種子法廃止による「食料への権利」の侵害は存在していないとして原告の訴えを棄却・却下するものでした。小山敬晴さん(大分大学経済学部准教授)は、この判断は誤りであると指摘し、次回の期日で意見書を提出します。生存権の視点から「食料への権利」はどのように位置づけられるのか、小山さんに伺います。
食料自給が危機的な状況での生存権の保障が問われている
「種子法廃止等に関する違憲確認訴訟」の第一審判決では、「確かに憲法25条1項に言う『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』の実現に向けては、一定程度の衣食住の保障が必要となることは否定できない」としながらも、種子法廃止による「食料への権利」の侵害については認めませんでした。しかし、この判断は誤りだと私は思います。
私の専門は労働法ですが、憲法25条で定められている生存権について考えると、歴史的に生存権は欧州において労働と密接なかかわりをもって形成されてきました。つまり「働いて収入さえ得られれば生存できる」という発想がもとにあり、そのうえで病気やけが、障がいなどの事情で仕事ができない、仕事が見つからない人たちに対して、国がお金や仕事を与えることで生存を保障するという考え方です。これを私は「古典的生存権」と名付けています。
しかし、労働をして収入を得ても、または生活保障の現金給付を受けたとしても、そもそも食料が手に入らない状況になれば生存できません。現状を見れば、気候変動による影響は世界中で起き、日本では農家の高齢化が進み、輸入に依存して食料自給力を失っています。いま農水省で不測時における食料安全保障に関する法整備が検討されていることからも、日本における食料の危機的状況は明らかです。
かつてとは異なり、お金があっても食料が手に入らなくなるかもしれない状況に置かれているなかで、人々の衣食住の権利、なかでも「食料への権利」を国がどう保障するのかが問われています。そうしたなかで生存権を考えるとき、貧困者の保護といった「古典的生存権」ではなく、人としてこの世に生まれた以上、その生存は絶対的に保障されるべきだという「自然権的生存権」の解釈に則った司法の判断が必要です。
この「自然権的生存権」の考え方が世界で初めて明文化されたのが、1948年の世界人権宣言および1966年の国際人権A規約における衣食住への権利(11条)でした。第一審判決でも衣食住の保障が憲法25条1項の内容を構成することを認めており、また日本は、食料への権利を明文で定めた世界人権宣言25条、A規約11条の条約締約国であることから、これらの権利を保障する義務があります。
食料・農業・農村基本法から見る種子法と「食料への権利」
では、「食料への権利」とは具体的に何かと言えば、国民の食料へのアクセス権の保障、つまり食料を手に入れられる状況が保障されていることであり、その保障のため国は食料生産体制を整備する義務を負っていると言えます。
第一審判決では、種子法のなかに「食料への権利」や「国民の主食を確保する」といった文言がないことを理由に、「食料への権利が具体化されていない」という形式的な判断がされました。しかし、日本の農業関連法の憲法のような法律である食料・農業・農村基本法(以下、基本法)には、2条に「将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならない」とあり、4条には「必要な農地、農業用水その他の農業資源および農業の担い手が確保され」、「(農業の)持続的な発展が図られなければならない」とあります。この農業資源のなかには、当然種子も含まれるはずです。
基本法の成立は種子法より後ですが、制定時に種子法が廃止されなかったことを考えれば、種子法は基本法の法秩序のなかにあると解釈できます。つまり、種子法も「食料の安定供給の確保」を目指す政策の一環だと位置づけられます。実際に、国や都道府県が予算をつけ、主要農作物の種子を生産する農家を指定し、低廉な農業資源として種子を提供してきた種子法の内容を見れば、食料への権利が具体化されていると言えます。
そして、「食料の安定供給の確保」がなぜ必要なのかといえば、憲法で定める(自然権的)生存権を保障するためであるはず。つまり種子法廃止は、国民が主要農作物にアクセスできる権利を保障するという義務を国が放棄し、生存権を侵害しているのと同じこと。このことを控訴審でしっかり主張したいと思います。
プロフィール
労働法学者
小山敬晴(こやま・たかはる)
大分大学経済学部准教授。専門は労働法。ワーキングプアなどの労働問題を考えるなかで、今の法制度にはお金の補償はあっても衣食住の現物を補償する仕組みがないことなどから、生存権と労働権の関わりに着目して研究。大分県での種子条例制定を目指し、市民団体「おおいた いただきますプロジェクト」を立ち上げて活動もしている。
Text: Mie Nakamura