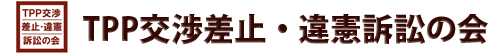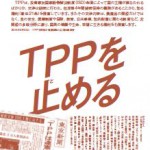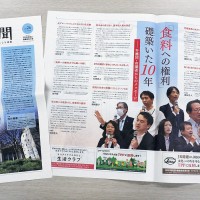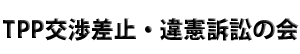種子法廃止違憲確認訴訟の控訴審判決は2025年2月20日、一審に続き「棄却」という結果に。原告団はこの判決を不服とし、3月4日、最高裁判所に上告しました。今回の判決の評価と上告の意義について、弁護団共同代表・田井勝さんに伺いました。
「前進も後退もなかった」わずか8ページの判決
法廷で判決文の短さを確認した瞬間、勝ち負けはともあれ、詳細な言及がないと分かり、非常に残念な思いでした。悔しい気持ちですが、これは裁判所として、種子法廃止について、地裁の判決以上に踏み込めないという判断なのだろうと分析しています。
もちろん、ここまでの到達点はあります。一つは、一審の地裁判決で、原告の一人である山形県の種子農家・菊地富夫さんが所有する圃場が、廃止された種子法に基づき県から指定される公法上の地位にあり、その権利の存在を裁判で確認する必要がある、すなわち「確認の利益」があると認定されたこと。種子法が廃止された以上、圃場指定されなくなる恐れがあり、山形県の種子条例による圃場指定はあっても財政的な保障はなく、現実的かつ具体的な危険があるという一定の被害を認めたということでもあります。こういった公法上の地位で「確認の利益」がある、つまり原告が争う資格があると判断した事例は、この種の裁判では例が少なく、大きなことです。
もう一つの到達点は、同じく地裁の判決で、「食料への権利」に関して一定の言及があったということ。判決文には「憲法25条の保障のために、一定の衣食住が必要になることは否定できない」との記載がありました。当たり前といえば当たり前なのですが、私たちの主張にまったく理解も親和性もなかったとしたら、このような言及はされないはずです。
確認しておきたいのは、こうした地裁の判決が、高裁判決で何も否定されなかったことです。つまり高裁では、前進はなかった一方で、後退もしなかったと理解すべきでしょう。
誤った憲法解釈、法解釈を正す。それが最高裁の役割
しかし、結局のところ、高裁は「食料への権利」を憲法上の権利として認めませんでした。この判断の誤りを正すには、最高裁に上告するしかありません。では、どのように闘うのか。最高裁では、高裁の原判決に誤りがあったかどうかだけが審議されます。その争い方には、「上告理由」と「上告受理申立理由」の2つがあります。
「上告理由」は、主に「憲法の解釈に誤りがあるか」を争うもの。今回は「食料への権利」を憲法上の権利として認めていない以上、明確に憲法解釈の誤りだと主張しています。
一方、「上告受理申立理由」は、「法令・法律の解釈に誤りがあるか」を争うもの。世界人権宣言25条1項には、「すべて人は、衣食住、(略)により、(略)十分な生活水準を保持する権利(略)を有する」とあり、十分な食料を誰もが得られる権利は国際法上も明記されています。そのうえで、わが国では1952年に主要農作物種子法が制定され、戦後の食料難を克服し国民に安定した食を保障することをめざしました。さらには、1999年にできた食料・農業・農村基本法(以下、基本法)により、良質な食料が安定的に供給されることは国民の権利であり、国の義務であると明記されました。まさにこれは「食料への権利」の具体化だと言い切れるはずです。食料への権利の主旨が改正後の基本法にも盛り込まれていることは、政府が国会答弁でも認めています。こうした基本法と種子法、食料への権利の関係性について、高裁は明らかに誤った解釈をしています。
食料への権利を全面的に裁判として扱うのは、恐らくこれが初めてのこと。最高裁の門戸は狭いのが実情ですが、私たちの主張は、決して荒唐無稽な話ではないはずです。
種子法が廃止されて以降、民間品種「みつひかり」の不正事件や、昨今の米不足、食品表示の厳格化など、食や農に関する社会問題が次々と沸き起こっており、この裁判をここで終わらせてはならないという原告の皆さんの強い思いがあります。裁判所には、そうした原告の不安や訴えをしっかり受け止めてほしい。
最高裁が判断を見直してくれる可能性がある際には、口頭弁論期日が開かれます。私たちの主張がしっかり届くよう、補充の準備書面を提出するとともに、弁論開催の要請行動をするなどして、さらに強く働きかけていきたいと考えています。私たちの提起が、今後も出てくるであろう食の問題の重要な出発点になるよう、最後まで闘い抜きましょう。
プロフィール
弁護団共同代表
田井勝
(たい・まさる)
1975年生まれ。香川県高松市出身。京都大学法学部卒業。2007年弁護士登録、横浜合同法律事務所所属。TPP交渉差止・違憲訴訟の会弁護団共同代表、建設アスベスト訴訟神奈川弁護団事務局長、自由法曹団神奈川支部事務局長。