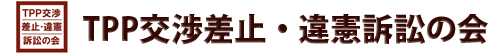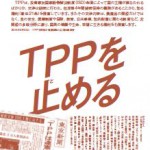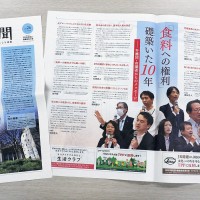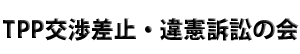種子法廃止違憲確認訴訟の上告を決めた思い、一審・二審との違いや上告審でのポイント、そしてあらためてこの裁判の意義について、消費者である原告の二人と弁護団の二人が座談会形式で話しました。
「えっ、これだけ?!」根拠なく棄却された高裁判決
野々山 東京高裁で判決が出たのが、今年の2月20日でしたね。言い渡しがあまりにも短くて、「えっ、これだけ?!」と傍聴席もザワザワしました。地裁の一審判決と比べてかなりレベルダウンした印象で、これは上告するべきだと、すぐにみんなで決めました。

原告 野々山理恵子(ののやま・りえこ)
東京在住。生活協同組合パルシステム東京元理事長。子どもの誕生を機に「安全、安心な食べ物を食べさせたい」との思いからパルシステム東京に加入し、組合員活動に携わる。
溝口 判決書も地裁は40ページ以上あったのに、高裁ではたったの8ページ。実は、私は控訴審にすごく期待していたんです。なぜかというと、裁判官が私たちの意見をちゃんと聞いてくれていたと感じていたからです。
小山 一般的に国家賠償裁判のハードルがとても高いことはわかっていました。ただ、私もやはり期待していた部分はあったんです。とくに最後の陳述で山田正彦さんが、なぜこの裁判を始めたのかを台本なしで克明に話されましたよね。それに裁判官も非常に真剣に耳を傾けていたように見えました。
そのぶん悔しさも大きかったわけですが、山田さんの言葉で訴訟の意義を再確認できたことで「また一から頑張ろう!」と、判決後の集会でもみんなの気持ちが盛り上ったのだと思います。

労働法学者 小山敬晴(こやま・たかはる)
大分大学経済学部准教授。専門は労働法。労働問題を考えるなかで、生存権と労働権の関わりに着目して研究。大分県での種子条例制定を目指し、市民団体「おおいた いただきますプロジェクト」を立ち上げて活動もしている。
岩月 高裁判決によってあらためて確認したのが、東京地裁での一審判決の水準の高さでした。一審判決では、種子法の制定過程から非常に丹念に経過を追ってくれて、何よりも採種農家である菊地富夫さんの「確認の利益」をはっきりと認めてくれた。この一審判決は判例として裁判所のデータベースで紹介されるくらい、非常にインパクトのある中身でした。
野々山 裁判や法律のことにあまり詳しくないので、上告にあたってあらためて弁護団のみなさんに教えていただきたいのですが、最高裁での上告審というのは、これまでの地裁や高裁での裁判とどう違うのでしょうか?
岩月 上告審は、裁判の三審制における最終審です。地裁(一審)、高裁(二審または控訴審)では、「こういう事実があったかどうか」という事実認定の審議をする。地裁での判決に不服があれば、控訴して高裁でさらに同じように審議を続けます。
一方、最高裁では、「高裁での判決(原判決)に憲法や法令解釈の誤りがあるかどうか」だけが判断されます。事実認定については基本的には高裁の判断を前提として争わず、たとえ新しい事実が出てきたとしても、それについて審議はしません。

弁護団共同代表 岩月浩二(いわつき・こうじ)
1955年愛知県生まれ。東京大学法学部卒業。弁護士。元自衛隊イラク派兵差止訴訟名古屋弁護団。TPP交渉差止・違憲訴訟、種子法廃止違憲訴訟弁護団共同代表。著書に『TPP黒い条約』(共著・集英社新書)。
野々山 高裁での判決が憲法解釈として間違っていないか、を審議するのですね。
小山 この裁判でいうと、高裁の判決では、食料への権利が憲法上の権利であることや、種子法が食料への権利を具体化したものであることが否定されました。でも、それは重要な憲法・法令解釈の誤りであるから、最高裁にもう一度判断してほしいと上告をしているわけです。
食料への権利は憲法上の権利。「人の尊厳そのもの」である
溝口 あらためて整理したいのですが、この裁判で私たちが主張しているのは、食料への権利が憲法上の権利であり、それが種子法で具体化されていること。そして、その種子法を立法目的もなく廃止したのは違憲だから、それによって損害を被った原告の国家賠償が認められるべきだ、ということですよね。
岩月 その通りです。
溝口 私は、この裁判が日本で初めて司法に「食料への権利は憲法上の権利である」と認めさせようとしている点で大きな意義があると感じています。そこで出てきたのが、「食料への権利は自然権的生存権である」という解釈ですが、これについてもう少し教えていただけますか?

原告 溝口眞理(みぞぐち・まり)
長崎県生まれ。埼玉県特別支援学校教員退職後、立教大学の池住義憲氏から様々な社会問題学び、2014年に同氏らとTPP交渉差止・違憲訴訟の会の立ち上げに参加。以後、ボランティアとして活動を続ける。
小山 食料への権利というのは、人が生まれながらに持っている最も基本的な権利のひとつで、日本国憲法においては25条の生存権としてとらえられます。
憲法の権利には、「自由権」(国にしばられない権利)と「社会権」(人間らしい生活を送れるように国が保障すべき権利)の2つあると言われますが、憲法25条に定められた生存権は、社会権であるととらえられてきました。そして、その生存権の範囲は国の裁量に委ねられているというのが、法律用語で「プログラム規定説」と呼ばれる考え方なのです。
しかし、食料への権利というのは国の裁量に委ねていいものではなく、もっと基底的な権利であり、従来のような生存権の解釈では限界が生じています。
野々山 そこで自然権的生存権という解釈が出てくるのですね。
小山 国にしばられない自由だけがあっても、食べ物がなくて飢え死にしそうな状態ではどうしようもありませんよね。衣食住が保障されて初めて、自由な表現活動や経済活動も可能になります。
そう考えると、食料への権利はすべての自由権を基礎づけるものとして、人身の自由を定めた18条にも相当する。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定めた25条、幸福追求権の13条など、複数の憲法の条項によって総合的に根拠づけられる権利だと言えます。
溝口 上告理由書のなかでも、自然権的生存権の解釈にたった食料への権利は、あらゆる自由権、社会権に先立つ「アプリオリな権利」だという表現をされています。
小山 私は食料への権利は、人の尊厳そのものではないかと思っています。環境権や平和的生存権などと同位で、「それがないと人間の自由が成り立たないもの」と言えるのではないでしょうか。このように自然権に則って生存権を解釈する必要性は、とりわけ農業生産基盤や環境の変化によって食料生産の不安定性が深刻化している現在の現実面からも裏付けられます。
溝口 それは、リアルでワクワクする解釈ですよね。
基本法との関係を否定した高裁の解釈は明らかに誤り
溝口 種子法が食料への権利を具体化したものであることについては、私たちは高裁でも「食料・農業・農村基本法」との関係をもとに主張してきました。
小山 一般に「基本法」と名の付く法律は、その分野について国の制度、政策、対策に関する基本的な方針を示すもの。つまり、食料・農業・農村基本法(以下、基本法)は、種子法に限らず、農業や食料関係の政策関連法の基本的な方向を示す法律であるはずです。その基本法第二条に「食料の安定供給の確保」ということが書いてあります。
野々山 まさに食料への権利を表す内容です。
小山 そのことを踏まえて種子法を見ますと、国は基本法によって「食料の安定供給の確保」という義務を負っており、その義務を履行するために種子法があって、主要農作物の種子の生産を国、都道府県に義務づけていると整理できます。
岩月 食料への権利の内容は、国際的に「利用可能性」「アクセス可能性」「持続可能性」「適切さ」の4つに整理されていますが、農業者が種子を使って安全安心な農産物を栽培することや、その農産物を消費者が購入して消費することを保障している種子法は、これら食料への権利の保障を目的としていると言えます。
溝口 でも、高裁では、種子法のほうが基本法より時期的に先に制定された経過があるので、種子法は基本法の理念を受けているわけではない、という国側の反論がありましたね。
岩月 基本法はその政策分野における土台であり、憲法のようなもの。基本法があとから制定されたからといって、種子法が基本法に基づかなくていいという話には絶対になりません。これは法体系上、火を見るより明らかなこと。基本法が制定されたあとに、種子法が何も手を加えられていないのは、それが基本法の理念に合っていたからだと解釈できます。
小山 これは高裁の解釈が明らかに間違っていると思います。
溝口 咋年5月の参院農林水産委員会で、基本法の改定案をめぐり共産党の紙智子議員が、「基本法の改正案は食料安全保障に関する国連食糧農業機関(FAO)の定義を踏まえたもの」という坂本哲志農水大臣の発言を踏まえ、「FAOの定義付けは1996年の世界食糧サミットのローマ宣言にあり、この宣言は基本的人権として食料への権利をうたっているのに、なぜ今回の改定案にこの権利という規定がないのか」という質問をしました。これに対し大臣は「国民一人一人がこれ(良質で合理的な価格の食料)を入手できる状態、これがまさに国が果たすべき役割であり、国民の皆さんが持っている権利であるという風に解釈している」と答弁した。これを聞いても、やっぱり私は1999年策定の基本法は国際的にも認められている食料への権利の内容を受けたものだと思うんです。
立法事実の裏付けを欠いていた種子法廃止法の成立は違法
野々山 国家賠償請求が認められるのは、違憲判決を得る以上にハードルが高いと聞きました。私たちは一審、二審で「具体的権利がない」と言われています。
小山 そうですね。法律的な考え方になりますが、社会権には抽象的権利と具体的権利の2つがあるとされています。抽象的権利というのは理念上のもので、一審判決でも「憲法25条の保障のために一定の衣食住が必要になることは否定できない」という言い方で、生存権のなかに理念上は「食料への権利」があると解釈できると言ってくれています。ただし、国に損害賠償請求をしようと思ったら、具体的な権利として主張できないといけません。
岩月 そこが難しいところで、「種子法廃止によって食料への権利が侵害された結果、私はこういう損害をこうむった」と個別具体的に主張ができないと、具体的権利性があるという風にならない。今回、原告の菊地さんの場合は、種子法廃止によって採種農家としての地位を失うという具体的な権利侵害にあった可能性があるということで、中身の判断に入ることができました。
高裁では種子法廃止法制定過程での立法行為に大きな不備があったことを訴えましたが、原判決はこれを退けています。しかし、種子法廃止法の立法事実が裏付けを欠いていたにもかかわらず、短時間の審議で法律を成立させたことは違法であり、国会議員が国家賠償請求の要件である「個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違反した」ことは明らかです。
溝口 種子法廃止法の立法事実は3点ありましたよね。
岩月 被告国の主張によれば、①「食料増産の目的が達成されたこと」②「種子生産の技術水準が向上したために、都道府県に一律に種子事業を義務づける理由がなくなったこと」③「多様なニーズに応えるために、民間ノウハウも活用して品種開発を強力に進める必要があること」の3点です。
①に関しては、控訴審の口頭弁論で山田正彦さんが言っていたように、農水省から出ている資料でも2023年から米の需要が伸びていくのに対して生産が落ち込んでいて米の需給が逆転していく試算が出ています。つまり食料増産が達成されていないことを農水省もわかっていた。②と③に関しては、わずかな国会審議のなかで三井化学クロップ&ライフソリューション(三井化学)のブランド米品種「みつひかり」が優れた民間品種の代表例として何度も取り上げられました。しかし、みつひかりは2023年に大規模不正が発覚し、事業から撤退しています。
野々山 本当に「みつひかり」の事件はひどい話でしたね。消費者の立場から言えば、昨年から米不足が続いて値段が上がって、食料増産の目的が達成されたとは思えない状況です。
岩月 政府はみつひかりの劣悪さを知っていた可能性があります。きちんと調査をすれば立法事実が成り立たないことが分かったと思う。こんなにずさんな法律制定はありません。みつひかりが粗悪品だということも、食料増産が達成されていないことも、ちゃんと調べていたらわかったはずです。非常に短時間で審議を打ち切っていて、国会議員の義務違反の程度は非常に大きいと言えます。
溝口 結局、これはTPPに伴う「結論ありきの廃止」だったのですよね。
岩月 国も、種子法廃止はTPP協定に関連した規制改革推進会議の決定によるものだと認めています。本来、種子法のような農政の基本にかかわる法律の廃止については食料・農業・農村政策審議会の諮問を経るべきなのに、それを飛ばして法案を出している。立法事実も目的もはっきりしないまま、トップダウンで公的種子生産体制の解体が行われたわけです。
消費者も生産者も流通もひとつながりの権利の共同体
溝口 種子法によって、種子農家、一般農家が質の良い種子を安く安定的に提供してもらって農作物を作り、それを消費者が消費するという、ひとつながりの関係が守られていました。そもそも食料への権利は、消費者だけでなく、生産者や流通など食料にかかわるすべての人の権利が組み込まれているものだと考えていいのでしょうか。
小山 私はそのように考えています。1961年に制定された「農業基本法」は、1999年に「食料・農業・農村基本法」へと名称が変わりました。その際に、流通の側面も強調され、かつ消費者の役割も強調された。生産、流通、消費というすべての側面を包含するのが、食料への権利なのだろうと考えています。
溝口 私がこの裁判を通じて学んだことは、私たち消費者の権利も生産者の権利もつながっていて一つのものだということです。同じ原告である種子農家の菊地さん、有機農家の館野廣幸さんの生産現場での苦労や誇りを知り、私たちは権利の共同体なのだと思いました。
昨年からの米騒動で「米が高くて困る」という消費者の声がニュースで取り上げられる一方で、米農家の苦労を知り現状を一緒に変えたいという考える人も増えています。みんなが食料への権利について知れば、こういうときにも消費者と生産者が対立せず、お互いの立場を理解して、それぞれの解決方法に向かって協力していけると思う。この上告は食料への権利のことを広げるチャンスだし、大きな意義があります。
野々山 日本でも食料への権利のことがもっと知られてほしいし、食料への権利を法律に明文化させたいですよね。市民同士で力をあわせて、まだまだ頑張っていきたいなと思います。
Text: Mie Nakamura