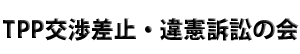「食料への権利は憲法上保障される」「主要農作物種子法(以下、種子法)の廃止は違憲」。こうした原告の主張に、被告・国は正面から答えようとしない。1月31日に行われた「種子法廃止等に関する違憲確認訴訟」第6回口頭弁論期日で、原告は、裁判所が違憲審査に踏み込むべき理由について、改めて主張した。弁護団共同代表の岩月浩二さんに聞いた。
立法過程に逸脱は? 違憲審査の基準とは
この裁判には、憲法上、二つの大きな意義があります。一つは、食料への権利が憲法上の基本的人権であることを認めさせること、もう一つは、種子法廃止法が食料への権利を侵害する憲法違反の法律であることを認めさせることです。今回、第5準備書面では、後者の違憲審査の基準について、その筋道を裁判所に示しました。
基本的人権は尊重されなければなりませんが、それを制限したらすぐに違憲となるわけではありません。とくに食料への権利の根拠となる憲法25条の生存権については、国家の干渉を受けない自由権と異なり、国家の作為によって保障される社会権であるため、違憲審査基準について特別な構成が必要になります。
一つの方法は、生存権を保障するために一旦具体化された制度を後退させることは、正当な理由がない限り憲法違反になるとする方法で、多くの憲法学説に支持されています。
もう一つの方法は、立法過程そのものを審査する方法です。これは、立法過程で正当な手続きがとられているか、考慮すべき要素が考慮されているかなど、国会が結論に至る過程を検討するものです。政策的な立法については、国会に立法裁量があることを認めた上で、立法過程に瑕疵があると認められる場合には、「立法裁量を逸脱して食料への権利を侵害した」として、違憲判断を行うことができるのです。
国会を欺いた種子法廃止は一種の“クーデター”
我が国の農政の基本は、「食料・農業・農村基本法(以下、基本法)」です。同法の基本理念には、優良な食料の安定的供給、農業の持つ多面的機能の充実、農村の振興などが定められており、農政の策定には、研究者や農業者、消費者、民間企業の委員などで構成される「食料・農業・農村審議会(以下、審議会)」の意見を聞かなければなりません。
食料自給率の著しい低下の中、主食である米のほぼ100%の自給率を維持してきたことには、基本法に基づいて具体化された種子法が圧倒的に寄与していました。このことは、被告・国も認めています。
ところが、農業政策の根幹をなす種子法を廃止する過程で、政府は審議会に一切諮問・付議していません。議論はもっぱら規制改革会議の農業ワーキンググループが主導し、そのまま国会に提出したものであり、政府による基本法の無視は甚だしいものがあります。
被告によれば、種子法廃止の目的は、種子事業への民間企業の参入を促し、市場化を図ることです。しかし、その目的のためには、奨励品種にかかわる制度の見直しで十分であり、圃場審査や種子の生産・普及も支えてきた種子法そのものを廃止するのは、立法目的から逸脱しています。
法案に賛成した議員の多くは、「種子法を廃止しても何も変わらない」との政府答弁を信じ、圃場審査など種子の管理は、種苗法改正により継続されると考えていました。しかし、改正種苗法に、種子法に代わる手当てはなされませんでした。種子法廃止法の附帯決議では、国による財政的裏付けを確保することを求めていますが、その根拠も何ら示されていません。本訴訟でも、原告らの指摘により、むしろ予算規模が縮小していることが判明しています。
こうした被告の姿勢は、国会答弁が、種子法廃止による種子事業の後退を危惧する国会議員をだますための、その場限りの虚言であったことを示すものです。規制改革ルートによる審議会の排除、立法事実の示されない審議を経て、国会からだまし取った種子法廃止とは、一種の“クーデター”とも呼ぶべきものなのです。立法過程に重大な瑕疵があったことは、疑いようがありません。
すなわち、種子法廃止法は、少数の企業利益に特化したグループが、法的・手続き的正義を無視して可決させたものです。国会の正常な審議過程を著しく機能不全に陥れ、少数の強者の利益を国会に押し付けることによって、国民の利益を蹂躙したという、民主政治・国民主権の侵害以外の何物でもありません。
その背後にあるのは、この裁判運動が明らかにしてきたTPP(環太平洋パートナーシップ)協定であり、「規制改革会議の提言に沿って必要な措置をとる」という日米交換文書で約束した流れでしょう。わが国の憲法体系と矛盾する、“TPP体系”とも呼べるその倒錯した立法のあり方について、司法は毅然と判断を示すときです。
プロフィール
弁護団共同代表
岩月浩二(いわつき・こうじ)
1955年愛知県生まれ。東京大学法学部卒業。弁護士。元自衛隊イラク派兵差止訴訟名古屋弁護団。TPP交渉差止・違憲訴訟の会弁護団共同代表。著書に『TPP 黒い条約』(共著・集英社新書)。